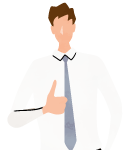ハイレベルな日本の介護実務を「習得させられない」現場に共通?「現場の空気」の理解不足&オノマトペによるコミュニケーション不足
自社業務の現場に就労してくれた海外人材にいかに活躍してもらうか。海外人材を活用するすべての事業者様の課題になっています。特に、最近海外人材の就労が増えている介護事業の現場での取り組みについて、そのポイントを紹介します。
現場と人が生み出す空間に慣れてもらうことを優先したコミュニケーション
生まれ育った自国を離れ、日本という外国で働きはじめる海外人材。事業者側としては現場での業務を早く覚えてほしいと考えることが多いと思います。その一方で、海外人材の活躍に向けて細かな業務知識を指導するよりも、まずは仕事の現場に慣れてもらうことを徹底して優先している介護事業者様もいらっしゃいます。
介護業務においては、利用者の方の表情やコミュニケーションの中から、その変化を捉えることが非常に重要になります。そのため、海外人材には細かな業務知識の指導や多くの利用者を介護するということは求めず、関わるユニット数を絞ることで現場の空間や人に慣れてもらうことを徹底しているそうです。
そうして現場や人に早く慣れてもらうことで、利用者への介護サービスの品質が向上し、海外人材の方自身もリラックスできるので、業務知識や日本語能力の向上スピードも上がっています。
現場の人手不足を補うために指導を急ぐよりも、海外人材の方のペースに合わせたサポートの方が、結果的に本人の成長に繋がったケースです。
複雑な日本語能力の上達のカギはオノマトペの理解促進
こ世界に数多くある言語の中でも、最も習得が難しいものの一つとされている日本語。ひらがな・カタカナ・漢字など文字が多いことや漢字の読みといった点が難しさの背景にあるといわれていますが、多くの海外人材を悩ませているのが「オノマトペ」の多さです。
オノマトペとは、「わんわん」「ワクワク」などのようにさまざまな状態や動きなどを音で表現した言葉を指しますが、施設利用者などたくさんの人と接する仕事をする介護事業の現場では、その理解の重要性も高くなります。
オノマトペは日本語に限ったものではなく、他の国の言語にも存在しますが、その数は多くの言語で数百個程度であるに対し、日本語は数千個あるといわれています。有名なオノマトペとして犬の鳴き声がありますが、日本語では「わんわん」、英語では「バウワウ」、インドネシア語では「グッグッ」というように、同じあるいは似た音や状態であっても、言語によってオノマトペは大きく異なります。
このように、ただでさえ日本語能力上達のハードルを高めるオノマトペですが、介護の現場では利用者の方から発せられるさまざまなオノマトペを正確に理解することが重要となってきます。例えば、利用者の方が頭痛を訴える時には「ズキズキ」なのか「チクチク」なのかで痛みの程度などを表現されますが、介護現場で働く海外人材がこれらのオノマトペを理解していなければ、そもそも頭が痛いことが分からなかったり、対応のやり方や緊急性などの判断を見誤ってしまいます。
また、私たち日本人としても、子供のころから使用してきたオノマトペを別の言葉で表現することはとても難しいものです。例えば、「胃がキリキリ痛む」ことをオノマトペを使わずに他人へ伝えようとしても、なかなか良い表現が思いつかないですよね。
そしてこのオノマトペの問題は、海外人材から発せられる場合にも生じます。海外人材の方が体調を崩した時などには、事業者側のスタッフが援助したり病院へ連れて行ったりすることがありますが、海外人材の方が自身の症状を自国の表現でしか伝えられなかった場合に、スタッフが対応や病院選びなどを間違ってしまうということが起きます。
このように日本語でのコミュニケーションにおいて重要な要素となるオノマトペですが、海外人材がしっかりと活躍している事業現場では、その教育に力を入れているケースもあります。海外人材にぴったりと伴走し、分からないオノマトペや単語が出てきた時には一つひとつ教えていく。事業者によるこうした丁寧な支援が海外人材の日本語能力を上達させ、彼ら彼女らの活躍を促しています。
日本のハイレベルな介護実務の基準をスタンダード化
介護事業の現場では日本語能力の上達に加えて、海外人材が介護という仕事の特性についての理解を深めるためのサポートも重要です。
多くの介護現場では、利用者のみなさんが日常の生活を送っています。その中では、着替えや入浴、排せつなど、利用者の方が羞恥心を感じる場面の介護は特に気を付けて行う必要があり、介護業務の代表的な特性の一つといえます。
プライバシーへの配慮や利用者本人ができることはなるべく自身でやってもらうなど、自尊心を傷つけない気遣いと対応が求められます。このような点は世界で共通している部分もありますが、介護業務に必要なスキルとして高めていく必要があります。
また、事業者側としても海外人材へ指導する際に注意が必要な点があります。着替えや入浴などのタイミングでつい指導に力が入ってしまうと、利用者の方をその状態で放置してしまうことがあります。こうなると利用者の方への配慮に欠けてしまいますので、一連の介護が完了した後に別途アドバイスをするなど、指導のやり方を工夫する必要があります。
この他、介護職が行ってはならない医療行為など、関連法規を理解してもらうことも重要です。たとえば、インドネシアでは聴診器を用いた血圧測定を介護職が行うことが可能ですが、日本では認められていません。
また、東南アジア諸国の介護現場では「ベッドに寝ながら洗髪介助することが多い」といった業務慣習の違いについても認識してもらうことが必要です。
以上のような点に留意しながら、利用者のみなさんの人生に寄り添う介護という仕事だからこそ習得しなければならないことを、海外人材へ優先的に指導していくことが大切です。
まとめ
この記事では、介護事業者が現場で実践している海外人材の活躍を促すサポートについて紹介してきました。みなさんの会社や事業の更なる成長に向けて、海外人材の育成やサポートなどについても、ぜひASIA HUMAN GATEWAYへご相談ください。他社様の事例などもご紹介しながら、海外人材の活躍に向けたお取組みをサポートいたします。