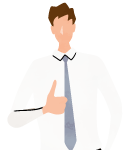その取り組み、ちょっと待って! 【突撃レポート】外国人材のホンネから見えてくる理想のサポートとは?
海外人材を迎えている介護事業者のみなさんは、業務と生活の両面でさまざまなサポートに取り組まれているものと思います。今回は、私たちASIA HUMAN GATEWAYが外国人材の方から直接伺ったお話の中から、みなさんが業務面・生活面で日頃から思っていることなどをトピックとしてまとめましたので、介護事業者のみなさんには、これからのお取り組みのご参考にいただければと思います。
外国人材のホンネ「正直、厳しい…」(業務編)
(1) 介護記録の書き方が分からない
介護記録は、利用者・ご家族とのコミュニケーションや職員同士の情報共有、ケアプランの検討などホンネされる重要なものですが、海外人材は慣れない日本語でこの介護記録を作成することに、難しさを感じることが多いようです。正しい文法で記入するところから始まり、「誰が・いつ・何をした」といった具体的な内容も必要であることから、その難易度は高いものがあります。事業者としては、これらの書き方に加えて、よく使用する単語や表現を教えてあげるなど、フォローが欠かせない業務といえるでしょう。
(2) シフト制による不規則な勤務時間が大変
海外人材はただでさえ慣れない環境で生活していますが、介護現場のシフト勤務への対応に苦労することが多いようです。勤務時間の長さは変わらないにしろ、始業・終業時刻が日によって変わることで生活のリズムが崩れ、体調を悪くしてしまうこともしばしば。事業者としては、日本での生活に慣れないうちは始業・終業時間を固定したり、本人たちの体調面を気遣ったりするなどのフォローが重要となります。
(3) 終業後も日本語勉強に精進
海外人材にとって日本語能力の向上は常に取り組むべき課題であり、1日の仕事を終えた後であっても勉強は欠かせません。私たちがお話を伺ったベトナムから来られた女性は、終業後の日本語の勉強として、1回2~3時間のオンライン授業を1週間に3~4回は受講しているとのことでした。慣れない環境の中で大変な努力をされていることが分かります。このような背景をしっかりと認識し、業務・生活の両面からのサポートを行うことが事業者には求められます。
外国人材のホンネ「正直、厳しい…」(日常生活編)
(1) 同居するメンバーに対する不安
海外人材は日本での居住において、同じく海外から来た人材と同居し共同で生活するケースが少なくありません。そのため、同居するメンバーはどのような人なのか、仲良くやっていけるかどうかなど、不安に感じています。そのような海外人材を迎える事業者としては、あらかじめ可能な範囲で同居メンバーの人となりを伝えたり、共同生活が始まった当初に関係を深められる機会を設けるなど、こうした不安をケアするサポートを行うと良いでしょう。
(2) 公共交通機関での移動の難しさ
海外人材は日本でマイカーを持つことはあまり無いため、買い物等の移動は基本的に日本人スタッフの送迎以外は公共交通機関を利用することが多いです。その際、バスや電車の路線や時間を確認し適切な便に乗るということが、私たちが思っている以上に海外人材にとっては難しさがあるものです。そのため、利用頻度の高い便やスマホアプリで調べる方法などを事業者が積極的に教えていくことが重要です。公共交通機関に対する不安が緩和されれば、海外人材は日本での生活をより一層頼んでくれるようになります。
海外人材のホンネ「けっこう楽しみ!」(日常生活編)
(3) 自国の料理を振舞う楽しみ
海外人材とは買い物や食事など職場を離れた場面においても積極的にコミュニケーションを図ることが大切ですが、海外人材が特に楽しめたと話すのが、日本人スタッフへ自国の料理を振舞うことだそうです。日頃さまざまなサポートをしてくれる日本人スタッフへの感謝を伝えられるし、故郷を思い出すことで良い気分転換にもなります。このような時間を共有するためには、日本人スタッフの方から「あなたの国の料理、食べてみたいな」と日常会話の中で伝えてみることも良いかもしれませんね。
(4) 海外人材が行ってみたい所
日本に高い関心を持って来てくれている海外人材は、日本の有名な観光スポットを多く知っていますし、いつか行ってみたいと思っていることが多くあります。中でも多くの海外人材が興味を持っているのが、やはり東京ディズニーランドです。日本で最も有名なテーマパークの一つであり、一度は遊びに行ってみたいと思っている方が多くいます。また、このようなテーマパークではなくても海外人材が好きなスポットが家電量販店です。自国にはない最新の商品に触れることができるので、みなさんに楽しんでもらうことができます。特に女性においては化粧品コーナーなどが併設されているとなおさらで、丸一日過ごしてしまうということもあるそうです。
まとめ
この記事では、海外人材が職場と私生活において日頃感じていることを詳細にお伝えさせていただきました。事業者あるいは日本人スタッフのみなさんが海外人材へのサポートを充実させていかれる際のご参考にしていただき、海外人材に寄り添ったサポートを通じて、彼ら彼女らの活躍につなげていただけますと幸いです。